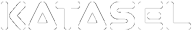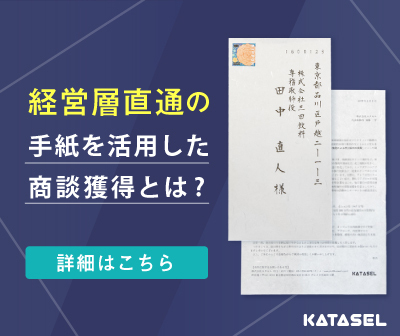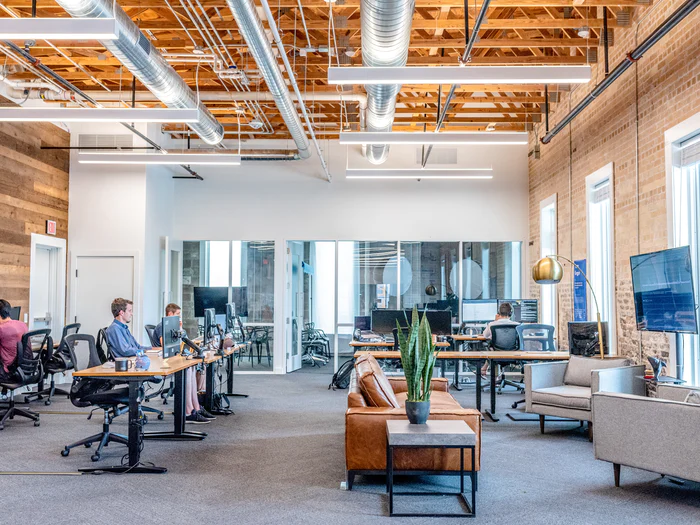必ずしも決裁者にアプローチすべきではない?決裁者にアプローチしたい商材とは

営業活動するにあたって、顧客が受注を決めるためには、決済者がゴーサインを出さなくてはいけません。そのため、営業は決裁者にアプローチすべきと考えられていますが、商材によっては効果的ではない場合もあります。
本記事では、決裁者にアプローチすべき商材の特徴をご紹介します。営業代行において、商材毎に業者を変えるべきかについても伺ったので合わせて参考にしてみてください。
Contents
決裁者の日常的な業務内容からアプローチすべきかを考える
決裁者という存在は、企業によって立ち位置が異なります。現場に積極的に参加している決裁者がいれば、現場と決裁者が分断されていることもあるでしょう。決裁者にアプローチすべきかを日常的な業務内容から考えていきます。
営業に関わっている決裁者の業務
営業組織に関わっている決裁者は、組織を俯瞰する立場でマネジメントに注力している場合が多いです。組織に属している営業パーソンの目標管理や行動管理、モチベーション管理など多岐に渡ります。営業パーソンの教育なども含まれるので、営業に関わるあらゆる業務に携わっています。
営業管理ツールとして、エクセルやスプレッドシート、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客管理システム)、マーケティングオートメーションなどを導入している場合は、ツールの管理や運用状況の把握も業務のひとつです。営業全体に関わるので、既存のSFAをSalesforceなどのツールと入れ替えたい、新たにCRMを導入したいというときには、決裁者が導入を判断することになります。
人事に関わっている決裁者の業務
人事に関わっている決裁者は、人事部部長やマネージャーなどが該当するでしょう。営業に関わっている決裁者と同様に、人事部全体を広い視野で見渡す役割を持っています。人材不足に対して、人事活動を直接的に行うのは、決裁者ではなく、チームメンバーであることが多いです。
具体的な業務としては、どのポジションに何人の人材が必要かといった課題発見・戦略立案などが挙げられます。具体的にどのように採用するかはメンバーに任せられるので、人事に関わるサービスを営業する場合には、メンバーと決裁者には現状の捉え方に差が見られるかもしれません。
企業規模によって決裁者の立ち位置が異なる
決裁者の立ち位置は、業務内容だけでなく、企業規模によっても違いが見られます。従業員数が少ない小規模な企業、起業して間もないベンチャー企業などは、決裁者が社長やマネージャーなど上層部でも現場の業務も兼務している場合が多いです。現場と同じ感覚を持っているので、決裁者にアプローチすることで、より案件化や受注につながりやすくなります。
一方、従業員数が100名以上の企業、数1,000名以上の企業においては、決裁者と現場に直接的な関わりが少ないでしょう。現場を俯瞰する立場にいる役員と現場を統率する課長・マネージャーといったように、現場と決裁者層が分断されている場合が多いです。
決裁者にアプローチすべき商材とは
業務内容や企業規模によって決裁者の立場は変化します。どのような商材であれば決裁者へのアプローチが効果的に働くのでしょうか?自社の商品・サービスがあてはまるかどうかイメージしながら参考にしてみてください。
決裁者のミッション達成に貢献する商材
業務内容にもよりますが、決裁者は組織を俯瞰する立場にいる場合が多いです。決裁者は組織をどう活性化するかを第一に考えて、営業を受けるか受けないかを判断します。そのため、決裁者が組織の活性化や業務効率化などのミッションを持っている場合、決裁者にアプローチすることで、ミッション達成を助けるので、成約の可能性が高まります。
SFAやマーケティングオートメーションといったツールの導入を例に挙げて考えてみましょう。ツール導入によって組織全体の課題解決ができるという商材であれば、全体をマネジメントする決裁者層にアプローチするのが効果的です。一方、ツール導入でアポイントの効率が上がるなど具体的な業務に関わる商材なら、ツールを実際に運用しているチームリーダーにアプローチする方が必要性を感じてもらえるでしょう。
決裁者と現場の関係性でアプローチすべきか見極める
決裁者のミッションが見えてこないときには、決裁者と現場の関係性に注目しましょう。判断基準として注目したいのが企業規模です。従業員数の多い大規模企業だと、前の項目で説明したように、決裁者はマネジメントを担当していることが多く、現場への関わりは少ないでしょう。
一方で、ベンチャー企業やスタートアップ企業など従業員が少なく、決裁者もメンバーと同じく業務に参画しているなら、現場の感覚に近いミッションを持っているはずです。この場合、直接社長などの決裁者にアプローチした方が商材の受注を決めてもらいやすくなるでしょう。
営業代行は商材ごとに業者を変えるべきか
営業は、自社組織で行うのが一般的ですが、営業代行業者を利用する例も増えています。自社の商材が複数ある場合、商材ごとに業者を変えるべきかどうかは気になるポイントです。なぜ業者を変えるべきかについて理由を解説していきます。
商材の特性に特化するために変えるのがおすすめ
複数の商材を決裁者や現場の担当者などに自社組織でアプローチするとき、商材ごとに知識を身に付けなくてはいけません。アポインターにリソースがあれば可能ですが、アポイント以外にも業務が多岐に渡るので、十分な知識を付けるリソースを確保するのが難しいです。得意としていない商材で説明がちぐはぐになってしまえば、営業が上手くいかないかもしれません。
営業代行業者は、業界・業種などに特化したノウハウを持っている場合が多いです。商材に合った営業代行業者を利用すれば、自社でリソースを割けなくても、専門性のある営業活動で受注を獲得できる可能性があります。
蓄積したノウハウを活用して商材に影響されない仕組みをつくる
営業代行には、ただ営業を任せるだけでなく、ノウハウを共有できる代行業者もあります。業者が行った営業活動のプロセスやノウハウなどを、レポートやミーティングで共有できるので、自社にはなかったノウハウを得られます。営業代行会社独自の販路を持っている場合も多く、新規顧客の開拓にもつながります。
蓄積されたノウハウ・販路を活用することで、商材ごとの知識やノウハウを自社に蓄積できます。自社組織で商材ごとのアプローチをできるようになれば、代行コストを削減しつつ、自社の営業力の強化を実現できるでしょう。
まとめ
企業によって決裁者の立ち位置が異なり、必ずしも決裁者にアプローチすべきとは限りません。決裁者は組織を俯瞰する立ち位置にいることが多く、現場と決裁者でミッションが異なる場合もあります。企業規模によって差があり、大規模企業なら決裁者と現場が遠いことがあり、決裁者へのアプローチが響かない可能性があります。一方で、決裁者が現場の業務に参加している場合には、現場と同じミッションを持っていることが多いため、決裁者へのアプローチが効果的です。
商材のアプローチに関わっては、商材ごとに営業代行を変えることも検討してみましょう。商材に特化したノウハウ・販路を活かした営業を行ってもらえるだけでなく、蓄積したノウハウを自社組織に反映させれば組織力の強化も望めます。自社の商材と決裁者のミッションを見極めて、的確にキーマンにアプローチしましょう。

・代表の経歴
大学卒業後、IT企業に入社し、飲食・小売店向けタブレット型POSレジのパッケージ・SaaSの提案営業、また、グループ会社にて、中小企業の経営者を対象に、自社開発CMS、BtoBビジネスマッチングサイトのアウトバウンド営業を担当させて頂きました。その後、IT企業に特化した人材紹介会社にて、外資系・日系IT企業を対象にエンジニア採用のコンサルティング営業を経験し、IT/WEB業界における無形商材の営業経験をいかして、2017年3月に株式会社カタセルを設立しました。
・LISKUL
大手企業とのアポ獲得なら「カタセル」!継続率87.5%の営業代行とは?
https://liskul.com/katasel-34173
・SalesZine
Sales Tech時代も「手紙」が最強の営業ツールなワケ
・SAIRU NOTE
セールスフォースも実践!大手企業とのアポイントを量産するCXO向け手紙施策のノウハウ詳細解説
https://sairu.co.jp/doernote/0160
◆実績
上場企業から数名規模のベンチャー/スタートアップ企業のご支援を通じて、大手・中堅企業のキーマンとの1000件以上の商談獲得の実績がございます。商材については、B2B SaaS、HR Tech、AIなどといった新規性の高いサービスから、システムの導入支援や業務改善、組織変革のコンサルティングなどといった大企業の大きな課題を解決するソリューションまで、一般的に、複雑で分かりにくいとされる無形商材の営業支援が中心となっております。月間の商談獲得件数については、営業マン1名でご訪問頂ける月間5件といったミニマムスタートから、月間1000通以上の手紙送付、商談獲得30件といった比較的大規模なアプローチまで、各企業様のご意向にお合わせしたボリュームで営業支援をさせて頂いております。弊社が獲得した商談経由の受注実績については、数百万円からLTVで考えると一千万円前後の高単価の商材を中心となっております。訪問から受注までのリードタイムは、商材によっても大きくことなりますが、平均的に3~6ヶ月で、早いものですと1週間前後で契約に繋がった事例から、長いものですと1年以上かけて契約に繋げるものまで幅広くなっております。受注率についても商材によって大きく異なり、受注率20%の事例もございますが、逆に数%の確率で大型商談を狙うものまで、商材の性質や単価、企業様の営業戦略によって大きく異なります。まとめますと、弊社は、ご依頼頂く企業様の規模は問わず、IT、マーケティング支援、コンサルティングなどの高単価の無形商材で、大手・中堅企業をターゲットにする営業支援を得意としております。